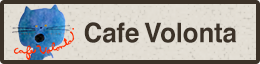びわこ文化公園ブログ | 文化・芸術・自然に親しもう!びわこ文化公園
びわこ文化公園BLOG
- ホーム
- びわこ文化公園BLOG
ブログ
BLOG
2022.10/12(日)
夕照の庭の花々
夕照の庭に、先月末から白いお花がたくさん咲いています!

ヒヨドリバナという花です。ハチやチョウなどの昆虫がたくさん集まってにぎやかな雰囲気です。
足元の方に目を落とすと…、

ほんのりと桃色を帯びて可愛らしいアキノウナギツカミです。茎には細かいトゲ
(痛くはありません!) があるようで、触るとくっつくような感触があります。
夕照の庭に生えているヒヨドリバナなどを含めた植物について、龍谷大学の先生や学生が『植物だより』で解説をしてくださっています。普段見かける植物のちょっとした豆知識や不思議な生態まで、奥深いところまで詳細に記載いただいています。
植物のことを知れると、いつもの散歩道がもっと楽しくなるかもしれませんね!是非じっくりご覧いただければと思います。
『植物だより』は、下記URLからご覧ください。
2022.10/07(火)
公園の困りもの
公園内でこのような紫色の花を見かけたことはないでしょうか。

紫色で子ぶりな花がとても可愛らしい印象です。
しかし、この花の種をご覧ください。

この種に見覚えのある方は多いのではないでしょうか。アレチヌスビトハギという名前でひっつき虫(くっつき虫)として有名です。
この時期草むらの中に入ると、後々服にびっしりくっついているなんてことがよくあるかと思います。外来生物で非常に繁殖能力も高い厄介者です。
園路側に伸びるものに関してはできるだけ刈り取るように心がけてはいるのですが、今の時期はあまり草むらの奥まで入らないことを強くオススメいたします…!
2022.10/02(木)
秋の野点を楽しむ会
本日、『秋の野点を楽しむ会』を夕照庵で開催しました!
すっきりと晴れた空の下で秋の空気を感じながら、遊茶流会による野点をお楽しみいただきました。

野点に合わせて、美術館企画展「石と植物」とコラボしたトークイベントも行いました。学芸員の三宅敦大さんにお越しいただいて、ここでしか聞くことのできないような展示物に関する貴重なお話をしていただきました。
また、夕照庵内の集会室では、苔アーティストの今田裕さんによる『苔テラリウム・ワークショップ』も開催いたしました。

ピンセットでの細かい作業に悪戦苦闘しながらも、皆さん思い思いの作品を作っておられました。ユーモア溢れる今田さんによるご指導で、常に笑いの絶えない楽しいワークショップになりました。

今回のイベントは、呈茶や美術作品、苔テラリウムを通して、文化や芸術、自然などの幅広い分野に触れることのできる贅沢な時間でした。これらの分野が皆様にとってより身近な存在になるよう、これからも様々なイベントを実施していければと思います。
2022.09/28(日)
ふんわりと秋の香り
雲高く透き通った空や涼しく吹き抜ける風に、秋の訪れを感じる日々です。
でも、秋の深まりを知らせてくれるのは、空や風だけではありません。公園では、あのふんわりと甘い香りが各地で漂い始めています。

秋の花といえば、キンモクセイを思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。甘く強い香りがとても印象的です。
キンモクセイは、春のジンチョウゲ、夏のクチナシと共に「三大香木」の一つと言われています。写真の通り、まだつぼみの段階でありながら、遠くからでも存在を感じさせる程の香りの強さです。
オレンジ色の小さな花もとても可愛らしいですよね。開花を楽しみに待ちたいと思います!
また、先々週のブログでツマグロヒョウモンのオスの写真を載せることができなかったのですが、無事撮影に成功いたしました!

比較するとこんな感じです。(左がオス、右がメス)
最近、夕照の庭で飛んでいるのをよく見かけるようになりました。ぜひまた観察してみてくださいね!
2022.09/23(火)
アケボノソウ
夕照の庭でクリーム色の可愛らしいお花を見つけました!

花びらの斑点を夜明け前のお星さまに見立て、アケボノ(曙)ソウというそうです。水辺などの湿った場所を好みます。花期は9月~10月頃で秋を告げる花の一つでもあります。
これから秋の花がたくさん見られる時期ですね!夏の暑さが過ぎて外で過ごしやすくなってきた頃ですので、是非秋の公園にもお越しください♪
2022.09/20(土)
秋の七草オミナエシ
西駐車場の奥にある臨時駐車場の更に向こう、鮮やかな黄色い花が遠くの方からでも確認できます。秋の七草の一つでもあるオミナエシです。

生き物の様子が穏やかになりつつある秋の公園をパッと華やかにしてくれます。近づくとチョウやハチなどが蜜や花粉を求めてたくさんやってくる様子も見られます。どんな昆虫が見つかるか観察しても楽しそうですね!

台風14号が通り過ぎて、日中でも肌寒く一気に秋が深まったような心地です。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですので、無理をせず身体を大事にお過ごしください。