【公園だより】お茶室について勉強 その②
みなさんいかがお過ごしでしょうか?
いい天気で気持ちいい日が続いてますね。
心地よい風が吹いてお花も喜んでいるようです。

さて、今回は「茶道」ってなに??
ということで勉強していきましよう。

「茶道」とは、
伝統的な様式にのっとって客人に抹茶をふるまう事で、「茶の湯」とも言います。
茶を入れて飲む事を楽しむだけではなく、生きていく上での目的・考え方、宗教、そして茶道具や茶室に飾る美術品など、広い分野にまたがる総合芸術として発展しました。
「茶の湯」では五感のすべてを楽しませてくれます。
視覚を楽しませる道具の美術工芸。
手に感じる茶碗のぬくもりや唇に感じる柔らかさといった触覚。
茶や茶菓子の味覚の楽しさ。
茶室にたちのぼる香のかおりを感じる嗅覚。
水を汲み上げる音や銅鑼のやわらかな響きの聴覚。
「茶の湯」は単にお茶を客人に振舞い、お茶をいただくだけではなく、
亭主自身も同じように客人から楽しませてもらうことが大切です。
そこに「茶の湯」の楽しみがあるといわれています。
「利休百首」というものがあります。
※利休百首とは
利休の教えである茶人の心得・作法などを
和歌に詠んだものです
「茶の湯とは ただ湯をわかし茶をたてて のむばかりなる事と知るべし」
この言葉を読むと、「ただ湯を沸かして茶を点てて飲むだけ」
ならば、お作法もお稽古もいらないのでは?
ついそう思ってしまいそうですがこの「ただ」ということが奥深いそうです。

これを説明する前にまずはお茶の歴史をご紹介します。
諸説ありますが
お茶の起源は紀元前2700年頃の中国といわれています。
日本に来たのは遣唐使が往来していた奈良・平安時代に、最澄(さいちょう)、空海(くうかい)などの留学僧が、唐よりお茶の種子を持ち帰ったのが、日本でのお茶の歴史の始まりとされています。
その頃のお茶は団茶(だんちゃ)といって、お茶の葉を蒸して固めたものを団子にしたもので、とても美味しいとはいえない代物だったようです。
さらに漢方薬とみなされていたため、薬として飲まれ、限られた階級の人だけが知るものだったようです。
やがて武家階級の間で広まったことで、より多くの人がお茶を嗜み始めたことが現在のお茶の歴史といわれています。
そこでお茶の世界に革命を起こした人物がいます!!
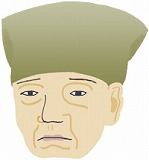 この人です!!
この人です!!
皆さんご存じの『千利休』です。
ということで
次回はこの『千利休』について少し詳しく紹介します。
お楽しみに♪
※現在は緊急事態宣言を受け臨時休園しております。
【公園だより】見浜園ご紹介 番外編 🌺つつじが綺麗に咲いています🌺
皆さん、こんにちは!
今日はとっても良いお天気で☀☀☀、見浜園内でつつじが綺麗に咲いていましたので、レポートします。
まずは、築山の川の流れとともに咲く、ピンクのオオムラサキツツジです。


ハス池の前に咲く、白とピンクのヒラドツツジです。


松籟亭を向こうに見てのつつじです。

船着場近くから平橋を向こうに見てのつつじです。

反対側から丸橋を向こうに見て。

ここからはつつじとのコラボ写真です。
まずは、上の池前のシバザクラとのコラボ!

松とのコラボ!(キリシマツツジ)

あやめとのコラボも!

最後は、カモとのコラボ?
気持ちよさそうに、(-_-)zzzです。

見浜園は緊急事態宣言を受け、現在は臨時休園しております。
実際にお見せできなくてとても残念ですが、この写真で是非お楽しみ下さいね。
【公園だより】見浜園ご紹介 その② 上の池にはたくさんの見どころが!
皆さん、こんにちは!
本日は、見浜園入園門の左手にある『上の池(かみのいけ)』についてご紹介します。

池の奥を見ると、池の向こうの山から湧き出でた水が滝となり、上の池に注いでおります。

滝口には、紅葉の枝が左右から2本滝にかかっています。
これは日本庭園の手法のひとつで、『飛泉障り(ひせんざわり)の木』といいます。
この飛泉ざわりの木とは、“滝の手前にそえて滝口を隠す木で深山の情景をかもし出す”手法です。
このような日本庭園において庭の景観の趣を出すために植えられる木(手法)のことを、『役木(やくぼく)』といいます。
湧き出る水は、井戸(地下100m以上)から汲み上げている地下水です。
地下深い水のため、温泉のような硫黄の臭いがします。このにおいがお好きな方にはどうぞ??
池の前の岩や石には、筑波山の岩(山の石)とゴロタ石(川の石)が使われており、自然がつくる造形美を醸し出しています。

また、上の池には、たくさんの鯉が泳いでいます。
見浜園に入らずとも鯉への“エサやリ”を楽しむことができる、隠れた人気スポットになっています。

特にお子様連れのファミリーには大人気です!
泳いでいる鯉は、ニシキゴイで、40匹以上います。
エサを求め鯉たちが一気に集まって来て楽しいですよ。

鯉のエサは1個100円で販売中です。お越しの際は是非お試しを!
※冬季は、鯉の健康管理のためエサやりは中止しています。
鯉は、寒くなるとエサを消化できなくなり、エサをたくさん与えると消化不良で死んでしまうのです。
前回(ここをクリック)“この上の池の水が川となり、見浜園内の下の池に流れつく”とご紹介しました。

日本庭園をよく人生になぞらえることがあります。
そういった観点からするとこの『上の池』は誕生の場と考えられます。
見浜園に入る前から、実は庭園散策が始まっているのです!
上の池は、入園料不要です。
いつでも散策できますので、お気軽にどうぞ!
次回は、見浜園の入園門についてご紹介する予定です。お楽しみに!
五月人形を飾りました!
皆さんこんにちは!
本日から5月ですね。みなさまお家でどのように過ごされているでしょうか。
5月5日は端午の節句の日ですねパークセンターでは一足先に五月人形を飾りましたよ!

この五月人形の鎧兜(よろいかぶと)には「体を守る」という願いが込められているそうです。
パークセンターでは今年も皆々さまの健康を祈願して飾らせていただきました。
また端午の節句には気軽にお家で楽しめる「菖蒲湯」(しょうぶゆ)というものもあります。
これは菖蒲(しょうぶ)の葉をお風呂の湯舟に浮かべて香りを楽しむものです。

実際にやってみるとスッとした独特の香りを楽しむことができます。
香りのおかげで気分転換できますよ!
まだもう少し家で過ごす日々は続きそうですが、このような季節の楽しみを大切にしていきたいですね。
ではまた次の投稿で!
【公園だより】見浜園ご紹介 その① 見浜園は『池泉回遊式』の日本庭園です。
皆さん、こんにちは!
さて、本日より、公園だよりにて、幕張海浜公園の人気のスポット『見浜園』の見どころや意味合いなどを数回に分けてご紹介・ご説明していきます。
まず、見浜園の概要ですが、見浜園は、1990年(平成2年)に千葉県により、国際交流の場『幕張新都心』に、日本の伝統的文化を伝えること、また接してもらうこと、を目的として設立されました!
総面積約1.6ha、『池泉回遊式』の日本庭園です。

今回はその『池泉回遊式』についてご説明します。
まず、前半の「池泉(ちせん)庭園」とは、伝統的な日本庭園の様式(3つあります)のひとつで、以下の庭園を言います。
自然の景色を模して造られた庭園で、山や川、海などがあり、「水」という要素が取り入れられています。


ちなみに、日本庭園の様式には他に以下の2つがあります。
「枯山水(かれさんすい)庭園」
水を用いず白砂や石などで自然の景色を表現した庭園で、「水」という要素がありません。
代表的な庭園としては、龍安寺(りょうあんじ)、西芳寺(さいほうじ)などがあります。
「露地(ろじ)」
茶室に付属して設けられた庭で、茶庭とも呼ばれるものです。
石張りの通路や飛石などを設け、自然の野山を模した茶室への道すがらの庭です。
また、池泉庭園には、庭園を鑑賞する方法によってさらに以下の3様式に分かれます。
「池泉回遊式(かいゆうしき)」(見浜園はこれ)
園路を歩きながら鑑賞する方式で、歩く地点毎に季節、時間、天候など場面場面の変化を楽しめます。
代表的な庭園としては、桂離宮や兼六園、六義園などがあります。
「池泉舟遊式(しゅうゆうしき)」
池の中を舟から鑑賞する方式で、池の中から全周の景色を楽しめます。
「池泉鑑賞式(かんしょうしき)」
座敷に座り眺めて鑑賞する方式で、絵画を見るように、じっくり一点から景色が楽しめます。

後々ご紹介しますが、見浜園では、上の池の水が川となり築山(山)を流れ、園中央の下の池(海)に流れつきます。
下の池には舟着場や州浜、出島・中島、橋が配され、また周囲には四阿など様々な意匠が施されています。数奇屋造りの茶室「松籟亭(しょうらいてい)」もあります。


まさに、池泉回遊式の日本庭園として、山や川、海、自然の景色が表現されており、歩きながら、四季折々に変化する景観の自然美、そして日本の伝統的文化を満喫することができます。
このような庭園の意味合いも知りながら、散策するのはいかがでしょうか?
次回は、この見浜園の入口左の上の池についてご紹介しますので、お楽しみに!
なお、見浜園は現在緊急事態宣言を受け臨時休園しております。
【公園だより】お茶室について勉強 その①
4月も下旬となり暖かい日が多くなってきました。 「見浜園」 「松籟亭」
幕張海浜公園には
その見浜園の中に
今回はいつもと趣向を変えて「松籟亭」をご紹介します。

「松籟亭」は京都北山杉を用いた数寄屋造りの本格的な茶室で、
低く延びるゆるやかな波を表現するような“むくり”のある
「銅板黒板一文字葺屋根」のかかる優雅な姿をしています。
茶室には小間・広間・立礼席・茶庭などがあり、
茶会や句会などを茶庭や池を眺めながらゆったりと楽しむことができます。
小間・・・ 4畳半以下の部屋を「小間」といい、草庵つくりでわび・さびを建物にあらわしています。
広間・・・ 書院造りの日本間で雪見障子を使用しています。
立礼席・・・明治の初期に外国の方々にお茶を楽しんでもらうため
椅子とテーブルでお茶を差し上げる方法として立礼式が考案されました。
松籟亭の立礼席は茶庭を楽しみながらお茶を頂くことができます。
茶庭・・・ 露地とも言われ茶室に付属して設けられた庭園です。
茶の湯の世界に誘われる大切なものとして位置づけられています。
松籟亭ではお抹茶と季節のお菓子のセットを召し上がっていただけます。
呈茶サービスについては「こちら」
他にも茶道に関するイベントなども開催しております。
ぜひ幕張海浜公園にご来園の際は松籟亭にもお越しください。
※現在は緊急事態宣言を受け臨時休園しております。
次回は「茶道」のことについてご紹介します。
よく分からないという方にも出来るだけ分かりやすくお伝えできるよう頑張りますので
楽しみにしていてください!!
みんなでつくるお花畑のチューリップ(4月15日現在)
「みんなでつくるお花畑」では、
チューリップ が咲いています♪




中央の赤、その左右に白と黄色のチューリップ。
昨年11月に実施しました
「チューリップの球根植付体験」で、市民のみなさんが
たくさん植えてくれました☆


向かって右と左の端には、
ピンクと黒紫のチューリップが。
花冠が開いて大きく見えるのは、
もうすぐ?

花畑の脇で、ハナズオウ(マメ科)
が咲いていました!
白い花が咲く木と、赤紫の花が咲く木がありますよ(^-^)



ボランティア花壇でも
チューリップとネモフィラがきれいに
咲いています。

こちらは シバザクラとネモフィラの
コンビネーション🌸

公園を明るく彩る春のお花
見ているだけで、心が和んだり
嬉しい気持ちになります♪
引き続き、季節のお花や自然情報を
アップしていきますので、
ぜひご覧ください(^-^)/
シバザクラが満開🌸🌸🌸です!
見浜園入口のシバザクラ(ハナシノブ科)が、見頃を迎えています。

今年は暖冬のせいか、例年より早く満開になりました!

一面ピンクの花じゅうたんが広がってます!

ネームプレートが埋もれそうです。

池のコイも、満開を喜んでいるかのように、元気、元気です。

お散歩で通りがかった際には、春限定で咲くこのシバザクラの彩りを是非ご覧下さい。
外出できない皆様には、この写真でお楽しみ下さいね。
【中止】春の野草観察会2020
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
中止とさせていただきます。
幕張海浜公園を歩きながら、
公園に住む虫や鳥、花などの生き物を
観察するイベント♪
クイズなどのゲームをまじえて、
楽しく身近な生き物について学ぶことができます\(^o^)/

小さなお子様から、大人まで楽しめる内容となっております。
ぜひ、親子やお友達家族と一緒にご参加ください^^*
シニアの方も大歓迎!
【日時】 4月26日(日) 10:00~12:00
※雨天時は中止
【集合場所】 幕張海浜公園Bブロック大芝生広場内
花時計近くの帽子屋根下に10:00集合
【参加費】 無料
【持物】 筆記用具、帽子、水筒、デジタルカメラ(あれば)、紙袋(採取した物をいれます。)
歩きやすい服装でご参加ください。
【注意事項】新型コロナウイルス感染症の影響で観察会が中止・内容の変更等の可能性がございます。
ご来場前にHpでご確認ください。
※当日ご参加の際には、咳エチケットなど感染症防止にご協力ください。
【申込・お問合せ先】
4月24日(金)までに以下の連絡先にご連絡ください。
県立幕張海浜公園みどりと海パートナーズ(パークセンター)
TEL043-296-0126 FAX043-296-0128
又はE-mail:contact@mokumoku-kun.info
見浜園⛄うっすら雪化粧⛄(3/29)
今日3/29(日)、見浜園にも⛄雪⛄が降り、うっすらと雪化粧しました!

平橋にも少し雪が積もってます。

東屋からの見浜園雪景色。

築山にもうっすら雪が。

スノーフレークが雪をかぶり、少し寒そうです。。
和名はオオマツユキソウ(大待雪草)、“雪の中で春を待つ草”、とてもピッタリの光景ですね。

桜はだいぶ散ってしまいましたが、珍しい桜とのコラボです。
舞っている白いものは、雪? 桜の花びら?


サクラはサクラでも、こちらは見浜園入口前のシバザクラとのコラボです。

今年のシバザクラ、例年より早く咲き始めています。
雪とのコラボは大変珍しいのではないでしょうか!

今日は天候等の理由で外出できない皆さま、
この写真で、見浜園の一年の中でもとても珍しい風景をお楽しみ下さいね。