【公園だより】お茶室について勉強 その⑥ ~花入~
こんにちは。
今日は雨が降って涼しく過ごしやすい気温でしたね。
さて、今回は“花入”(はないれ)です。
花入(はないれ)はその名前の通り花を入れる道具です。
いわゆる花瓶のことです。

金属・磁器・陶器・竹・籠製のものなどがあります。
金属製のものや、中国製の陶磁器などを「真」、上釉(うわぐすり)のかかった和物の陶磁器を「行」、竹・籠・瓢や上釉のかからない陶磁器などを「草」だとされています。
この「真・行・草」は見浜園のアプローチの飛び石でもありましたよね。
書道の「真書(楷書)」「行書」「草書」の三体と同じ意味合いです。
こうしてみると色んな意味があって言葉って面白いなと思います。
花入には、中釘や床柱の花釘に掛ける「掛花入」(かけはないれ)

床の天井や落掛などから吊るす「釣花入」(つりはないれ)
床に置く「置花入」などがあります。

ちなみに中釘(なかくぎ)とは、床の間正面の壁の中央に、掛花入を掛けるために打つ折釘のことです。
落掛(おとしがけ)とは、床の間の上部の辺りにある横木のことです。
この落掛に釘を打ってそこに「釣花入」を掛けます。
置花入は床が畳敷きの場合は下に薄板を敷きますが、籠花入の場合には薄板は用いません。
同じ素材でもさまざまな形があるため機会があればいろんな花入れを探してみてもおもしろいですよ♪
みなさまに安心してご利用いただけるよう
営業再開に向けてスタッフ一同準備を進めております。

なお、見浜園は現在緊急事態宣言を受け臨時休園しております。
5月・園内のお花情報(5月18日現在)
公園内のお花の様子をお伝えします(5/18現在)🌼
「みんなでつくるお花畑」(Bブロックマリンデッキ階段横)では
チューリップが終わり、種から播いた
ジャーマン・カモミール(キク科)
の白い花が たくさん咲きました(^-^)


花の頭からは 青りんごのような 甘い香りがします☆
Bブロックのボランティア花壇では
ブルー・デイジー(キク科)


シャスター・デージー(キク科)


タツタナデシコ(ナデシコ科)


宿根バーベナ(バーベナ・テネラ種、クマツヅラ科)


ハーブの
センテッド・ゼラニウム(フウロソウ科)


葉が風に揺れると、甘い香りが漂います♪
クリーピングタイム(シソ科)

小さく可愛らしい花が 咲いてます♪
低木の
マルバシャリンバイ(バラ科)

春から初夏にかけて 新緑の中で
次々と色々な花が咲き、公園の景色が
色鮮やかになりますね。
引き続き季節のお花や自然情報を
アップしていきますので、
ぜひご覧ください(^-^)/
5月・見浜園のお花情報(5月17日現在)
休園中(5/17現在)ですが、
見浜園のお花の様子を
お伝えします(^-^)
草花では、
マツバギク(ハマミズナ科)

アヤメ(アヤメ科)


シラン(ユリ科)


(白い花が咲く品種もあります)
が咲いていました。
花の木では、
ヤマボウシ(ミズキ科)

州浜側のあずまやでは、
ハコネウツギ(スイカズラ科)
が咲いています。


時間がたつと、白からピンク→赤へと
三色に変わり咲きする、鮮やかな花木です。

モミジも紅葉していました。
(シダレモミジ)


(ノムラモミジ)


秋だけでなく、若葉が更新する新緑の季節にも
紅葉します。
そしてこれから、初夏の花である
アジサイや ハナショウブも咲き始めますので、
また公園ブログでお伝えしますね(^-^)/
※見浜園は現在緊急事態宣言を受け臨時休園しております。
【公園だより】お茶室について勉強 その⑤ ~香合~
こんにちは。
本日はとても良い天気でしたね♪
最近は暑くなったり涼しくなったりしたり、
あとはマスクをつけていると熱がこもってしまうので
みなさんも水分補給などの体温調整は適度にしてください。
さて、今回の茶道具の紹介は“香合”(こうごう)です。

香合(こうごう)は、「香」を入れるための小さな蓋付の器です。
香は風炉や炉の中で焚いて、香りを楽しむとともに、部屋に清浄感を与えます。
炭手前(すみでまえ)のときに、炭斗(すみとり)に入れて席に持ち出します。
炭手前がない場合は床の間に花入(はないれ)とともに飾ります。
※炭斗(すみとり)・・・炭を入れて席に持ち出す入れ物
風炉の季節(5~10月)には木地(きじ)、塗物(ぬりもの)等の香合を使い、
白檀(びゃくだん)などの木製の香を入れ、

写真は風炉の例で左側の窯みたいな形状のものが“風炉”です
炉の季節(11月~4月)には陶磁器のものを使い、練った香を入れます。

“炉”は囲炉裏(いろり)の略した呼び方です。
ちなみに“お香”には色んな種類があります。
直接火をつけるもの・常温で香るもの・間接的に熱を加えるものなど・・・
また、原料によってもさまざまな違いがあります。
これはキャンドルやディフューザーやフレグランスオイルなどがある
“アロマ”と共通する部分がありますね。

“お香”は少しですがパークセンターでも販売しておりますので
立ち寄られた際には是非見てみてください。
次回は「花入(はないれ)」のご紹介をします。
なお、見浜園は現在緊急事態宣言を受け臨時休園しております。
【重要】幕張海浜公園 新型コロナウィルス感染防止に伴う施設臨時休業のお知らせ(5/16更新)
【5/16更新】※5月18日(月)より
A・Bブロック駐車場
の営業を再開します。
(Cブロック駐車場は引き続き休業中)
※過密な状況が確認された場合は、駐車台数の制限や再閉鎖をすることがあります。
新型コロナウイルス感染防止対策の為、 4月 8日(水)より当面(1ヶ月程度)、以下の施設を終日休業いたします。
【対象施設】
①見浜園・松籟亭(茶室)
②Cブロック駐車場 → A・B・Cブロック駐車場
③BBQガーデン
【休業期間】
2020年(令和2年) 4月 8日(水)より当面の間(1ヶ月程度)
上記の決定は、日本国政府の緊急事態宣言を受け、千葉市から指示のあったものです。
また、今後の状況により、休業日がさらに増える可能性もございます。
急な決定でお客様各位には大変ご迷惑をおかけし申し訳ありません。
何卒ご理解・ご了承くださいますようお願い申し上げます。
見浜園やその他エリアでの撮影など行為申請についても、当面の間は実施出来ません。
既に申請のあった方には公園から個別にご連絡をさせていただきます。
【公園だより】見浜園ご紹介 その⑤ 日本の名園の要素がいっぱい、見浜園
皆さん、こんにちは!
本日は、見浜園の築山などについてご紹介します。
アプローチを抜けると、いよいよ園内が開けてきます。

ここから左手に向かいます。
パンフレットにも記載の通り、見浜園は、時計廻り(右廻り)での散策が標準の順路になっています。
左手に進み、右側にあるのが松籟亭です。

先の公園だより『お茶室について勉強 その①』でもご説明しましたが、松籟亭は、京都北山杉を用いた数寄屋造りの本格的な茶室です。
※数寄屋造り:数寄屋つまり茶室を作る際の特徴を取り入れた建築様式。
表門は『大門』と呼び、日本一の名園と言われる京都の「桂離宮」の表門を模した造りとなっています。

※桂離宮:17世紀に八条宮初代智仁親王と二代智忠親王によって造られた日本庭園。
垣根は、『桂垣』という種類で、これも桂離宮正門の「桂の穂垣」と同じ仕様となっており、丸竹をふたつに割ったものを縦に使い頭を斜めにカットしてあるのが特徴です。

左側には築山(つきやま)があります。

『築山』とは人工的に作られた山を言いますが、日本庭園では観賞用としてのものです。
この山の一番高い部分が標高3.8mで、見浜園の中での最高点になります。
先にご紹介した上の池より注ぎこんできた川の流れは、この築山で二つの流れに分かれます。

ひとつは、山あいの穏やかな渓流となり奥の中の池に注いでゆきます。

もうひとつは、築山の斜面を回るように難所をくぐりながら下の池へと流れて行きます。

これも先に“日本庭園は『人の人生』になぞらえる”とご説明しましたが、まさにこの二つの流れは誰もが経験するものではないでしょうか?
築山の右手奥には、東屋があります。

この高台に配された東屋は、庭園全体を見渡すことができ眺めのよいスポットです。
この東屋も、先の桂離宮や修学院離宮(これも京都)にも見られます。
※東屋(あずまや):“四阿”とも書きます。庭園などに眺望、休憩などの目的で設置される簡素な建屋。
このように、見浜園のところどころに、日本の名園の要素が取り入れられています。
このようなことを感じながら、散策するのも趣きあるのではないでしょうか?
次回も、引き続きお楽しみに!
なお、見浜園は現在緊急事態宣言を受け臨時休園しております。
【公園だより】お茶室について勉強 その④ ~軸~
こんにちは。
前回までは茶道についての紹介をしました。
今回からは“茶道具”についてひとつずつご紹介していきます。
今回は「掛軸(かけじく)」です。
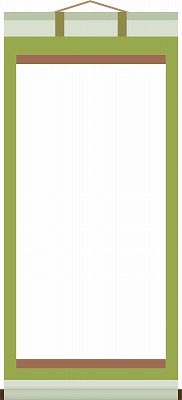
「掛軸」は床の間に掛けて使われるもので、「掛物(かけもの)」ともいいます。
茶道において、「掛軸」を用いる意味は二つあります。
一つは、<茶席の趣旨や目的、あるいは亭主の心構えなどを示す>というもの。
そしてもう一つは、<季節感の演出>です。
このうち前者では、茶席をどのような考えで設けたのか、どんな気持ちで過ごしてほしいかといった、客に対する亭主のメッセージがこめられます。
掛軸は禅語を書いた墨蹟(ぼくせき)が用いられることが多く、
「日日是好日(にちにちこれこうにち)」や
「和敬清寂(わけいせいじゃく)」など、
茶道の精神を象徴するような言葉が好まれます。
一方、後者の季節感については、日本における多くの伝統芸能や文学と同様に、四季折々の自然や風物を鑑賞することに重点が置かれます。
画であればもちろんですが、書であっても言葉の選び方によって季節を感じさせるよう演出をします。
さて、「掛軸」には文字を書いたもの、絵画を描いたもの、文字と絵画の両方が書かれたものがあります。
文字を書いたものには
禅語を書いた「一行物(いちぎょうもの)」「横物(よこもの)」など、
和歌や発句(ほっく)を書いた「懐紙(かいし)」「短冊(たんざく)」など、
昔の茶人が書いた手紙などがあります。
絵画には唐絵(からえ)、大和絵(やまとえ)などがあります。
文字と絵画の両方が書かれたものは「画賛(がさん)」といいます。
こういうことからもし今後茶室に入る時には、まずは床の間に飾られた掛け軸を見てみるとおもしろいかもしれませんね。
解りやすい言葉もあれば、聞いたことがない文字が並び、解説されてもなおわからないことも多いですが、それでも大丈夫です。みんな一緒です。(笑)
ただ、大切にしたいのは、先生や、亭主がそのお茶席に、この「掛軸」を選んでいることには理由があるということをしっかりと理解し、先生や亭主の気持ちを感じ取り、感謝の気持ちを持ってお茶席に臨むことです。
それでは今回はここまで。
次回の茶道具はお香を入れる
「香合(こうごう)」です。
なお、見浜園は現在緊急事態宣言を受け臨時休園しております。
【公園だより】お茶室について勉強 その③
こんにちは。
今回は前の「お茶室について」の公園だよりでお知らせしました
「千利休」について勉強をしましょう。
前の記事はこちら
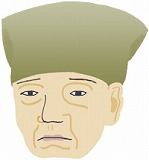
「千利休」という名前は当時の天皇から与えられた名前で
歳をとってから使われた名前です。
その前は宗易(そうえき)、幼い時の名前は田中与四郎といいます。
出身地は大阪の堺市です。
当時茶道は、高価な茶碗や、ハデな演出でされていました。
豊臣秀吉が『黄金の茶室』を作ったことは有名です。
また『闘茶』という、茶の種類や水を当てるギャンブルまで流行りました。
“利き茶”みたいなものですかね。
利休の「詫び茶」ではそういった高価な道具や、
ハデな演出など、無駄をすべて取っ払ってお茶そのものを楽しむというものでした。
織田信長は「茶の湯」をとても大切にし、戦しかしらないような人にも茶道を
ススメました。お茶を通して教養を付けてほしかったのです。
また新しいもの好きであった信長は、茶器などの道具にもかなりこだわるほど
茶道を大切にしていました。
秀吉の時代になると、秀吉がますます「茶の湯」に力をいれたので、
お茶の世界でリーダー的な役割だった利休は力も持ち、秀吉からも大切にされました。
「秀吉に意見を言えるのは利休しかいない」という、史料まであるということから、その凄さがうかがえます。
そしてわずか“2畳”ほどの茶室「待庵」(たいあん)を創作しました。
この“待庵”広さも驚きますが入口に“にじり口”という入口があります。
この“にじり口”は低さに驚きます。
「松籟亭」の小間にもこの“にじり口”はあります。

外観
写真の中央にある木の板の部分が“にじり口”です。

中から見るとこういった感じです。
左側の正方形に開いているところが“にじり口”です。
なぜこんな入口を作ったのか??
それは利休がいた戦国時代は主従関係が強い時代でしたが、
茶室の中ではすべての人が平等ということを示すために入口を低くしたそうです。
これならどんなに身分が高い人でも、刀を外し頭を下げなくては茶室に入ることはできませんよね。
そんな大活躍だった利休ですがある日秀吉から切腹を命じられます。
そこで利休は「茶室にて茶の支度が出来ております」と言い使者に最後の茶をたてた後、利休は一呼吸ついて切腹しました。
千利休が愛した
“茶道”
次回からは茶道具に触れながら茶道を勉強していきましょう。
なお、見浜園は現在緊急事態宣言を受け臨時休園しております。
【公園だより】見浜園ご紹介 その④ 隠れた演出が盛りだくさんのアプローチ
皆さん、こんにちは!
本日は、見浜園のアプローチについてご紹介します。
北門を潜ると、“いらっしゃいませ!”と言わんばかりに、石畳のアプローチが見浜園へと誘(いざな)います。

この石畳は『飛び石』の一種です。
飛び石とは、日本庭園の通路などに飛び飛びに配置され情緒を醸し出す石で、千利休によって、茶室に通じる茶庭に歩幅ほどの間隔を開けて置かれた平らな石が始まり、と言われています。
庭の苔や芝生を踏まないように茶室まで誘導する目的や、飛び石をゆっくり渡りながら庭の眺めを楽しんでもらう意味合いがあります。
日本庭園の飛び石には以下の3種類があります。
・「真」(しん):切り石のみの飛び石
・「行」(ぎょう):自然石+切石の飛び石
・「草」(そう):全て自然石で出来た飛び石
書道に、「真書(楷書)」「行書」「草書」の三体があることと同じ意味合いです。
この石畳は、『真の飛び石』となります。目地は丁字でずれないようにしております。
また、小堀遠州という有名な江戸初期の茶人(庭作りも行う)が、この切り石のみの(真の)飛び石を好んで採用したことから、『遠州好みの真の飛び石』といいます。
アプローチの右手には、かなり背の高い植栽があります。

自然の美しさを損なわないように風景を調整することを『修景』といいます。
この植栽は、修景植栽と言え、庭園に入った趣きを損なわないよう、周辺のビル群を隠す役割をもっています。
つづいて、アプローチの左手には、大人の背丈ほどの生垣があります。

この生垣は「金閣寺垣」と言われるもので、京都の金閣寺の滝口にある竹垣と同じ手法によってくみ上げた生垣です。
竹垣は低く上部にかぶせ竹を施しています。垣根の上部に半割りの竹を掛けているのが特徴で、造形的に格調が高いとされています。
この竹垣や生垣の隙間から向こうの園内(築山)がチラチラ見えます。

これにより、これから散策する庭園がどんな趣きなのか、想像力と期待感を膨らまされるのです。
このアプローチを進むと、くの字型に少し左に折れていきます。

折れた先を進み振り返ると、北門やその外が見えなくなります。

『屈曲の意』といい、外界とお別れし、この庭園の世界にじっくり入りこんでいただくための工夫のひとつと言えるでしょう。
このように、アプローチには、お客様を向かい入れる様々な(エンターテイメントで言うところの)“演出”が取り入れられています。
このような造園者の想いや工夫も知りながら、アプローチを歩いてみるのも感慨深いのではないでしょうか?
次回も、さらに見浜園の各所を紹介していきますので、引き続きお楽しみに!
なお、見浜園は現在緊急事態宣言を受け臨時休園しております。
【公園だより】見浜園ご紹介 その③ 格式高い見浜園の入園門『北門』
皆さん、こんにちは!
本日は、見浜園の入園門についてご紹介します。
まず、見浜園に入園するには、入園料が必要になります。
料金は、大人100円、小中高校生50円となります。
(年齢65歳以上の方は身分証明書をご提示により、障がい者の方及びその介護者の方は障がい者手帳をご提示により、入園料が無料になります。)
この入園門右手の券売所にて、お支払い下さいね。

見浜園の入園門(通称『北門』と呼ばれています)の屋根は、なだらかな曲線の銅葺き(ぶき)となっています。

『銅版一文字葺き』という皇族や摂家などの御所に用いられた日本家屋の伝統的な工法を採用しており、日本の伝統美も感じさせつつ、国際交流の場『幕張新都心』を意識して現代風にアレンジされたものになっています。
また、銅にはイオン効果があり、木造の建築物の柱の根本や大切な部分を銅板で保護すると、このイオンが溶け出して木材の腐食菌に対して殺菌作用をもたらせます。
すなわち、木材がより長持ちし、建築物を守る事になります。
北門の屋根は、このような建築の工夫(技術)で劣化を防いでいます。
さらに、北門の塀は、定規筋(じょうぎすじ)と呼ばれる何本もの白い水平線が引かれた土塀になっています。

これは、単なるデザインではなく、『筋塀(すじべい)』といい、御所・宮家などしか許されないという塀を模したものです。
筋の数は格式により異なり、五本が最上となります。
このように門だけとっても、見浜園に、格式ある日本の伝統文化をお伝えしようとする想いが感じられますね。
このような意味合いも知りながら、門を潜ってみるのも趣きがありますよ。
なお、見浜園は現在緊急事態宣言を受け臨時休園しておりますが、
通常時の開園時間は 8:00~17:00(入園は16:30まで)となります。
年末など不定期に定休日がございますので、予めホームページをご参照下さいね。
次回は、いよいよ見浜園の内側を紹介していきますので、引き続きお楽しみに!